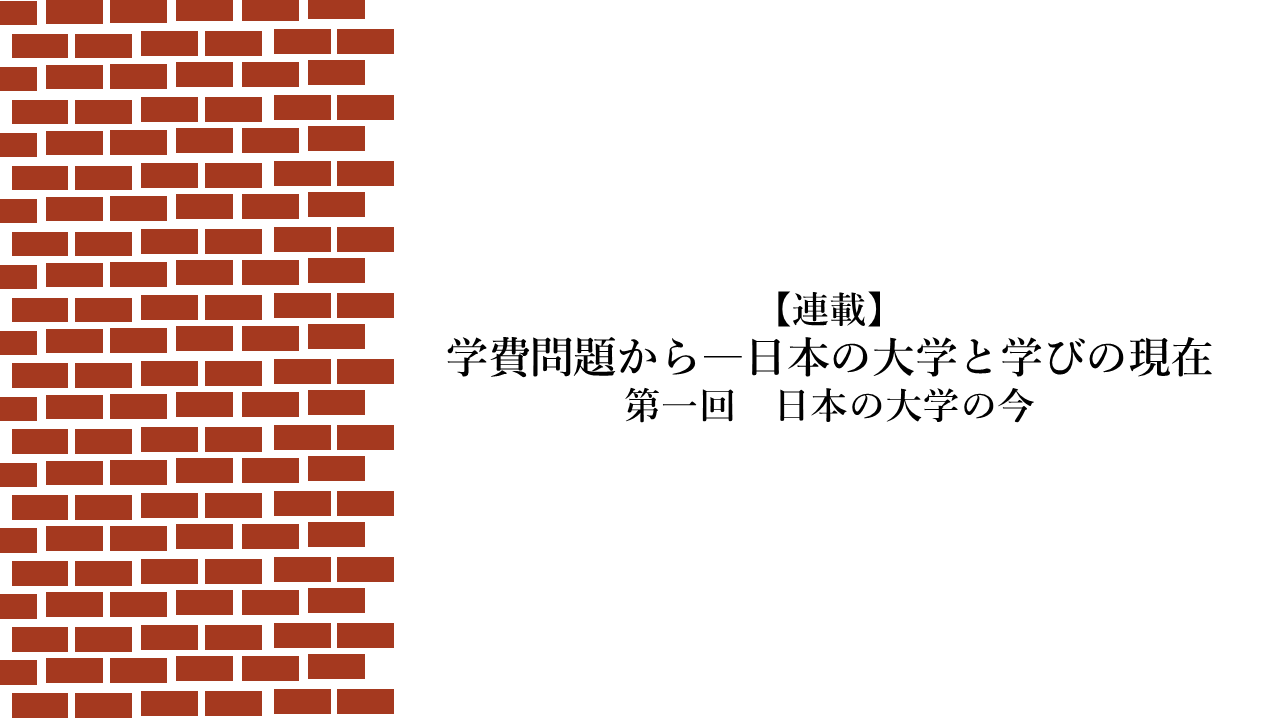
今年大学が大きく揺れた。東京大学が20年ぶりに授業料を引き受けたのである。大学の学費値上げについての議論は長年行われてきたが、ついに値上げという形で結論が出た。国や大学ではなく、学生がその尻拭いに当てられたのである。思えば、今年度上半期は学費についてかなり大きな動きのあるものであった。
3月、本校塾長により提言されたいわゆる「150万」の発想が世論を沸かしたことは記憶に新しいが、他にも6月7日には国立大学協会が大学の財務状況について「限界」と発言し、値上げへの理解を求めたことも世間を驚かせた。7月にはその影響もあってか文部科学省が国立の学費値上げに対して有識者会議を設置し、8月には日本私立大学連盟から、国立大学の学費の上限規制撤廃を含む提言を発表。もはや国私ともに限界との声が上がる中、9月24日に東京大学が来年の授業料の値上げを正式に発表した。
しかしそもそもなぜ大学は困窮しているのだろうか。複数挙げられる理由のなかでとりわけ大きいのは予算の分配である。
日本社会における国立/私立大学
2004年の大学法人化後、国立大学を含める日本の大学に対して国からはそれぞれ助成金が交付されている。2023年度の国立大学運営交付金は約1兆600億対して、私立大学等経常費補助金は約2976億円であった。一方、これに対して現状日本の大学生のおよそ7割は私立大学に在学している。
まずここから明らかなのは、国はただ学生に金をかけるというよりは、そうでは無い別の客体、すなわち国立の研究および教育に金をかけていると言う事実である。実際2023年時点では、OECD内で日本の大学の私費負担率はイギリス、コロンビアにつき第3位と言う高順位に位置しており、私立大学の平均学費は年々上昇の一途を辿っている。また、これについては、教員の数においても同様の結論を見ることができる。
2023年のデータでは、私立大学の教員一人当たりの学生の数は、国立大学の約2倍であり、教育の質的観点から不安の声が上がっている。このように日本の大学の現状と言うのは、比較的少ない資金と人材によって運営される私立大学が日本の教育機会を担保している一方比較的多い資金と人材で運営される国立大学が、国としての高等教育や研究の質を担保している構造であると言える。
学費問題から
さて、今回の東京大学の学費値上げ騒動は日本の最高学府の値上げと言う点で非常にシンボル的なものである。しかし立ち止まって考えてみれば、国立大学の値上げは今回が初めてではない。千葉大学や一橋大学を始め、既に六校が値上げを実施しているし、繰り返すが、そもそも私立大学では学費値上げが常態化している。また今回の問題について世間では「私立大の数削減」や「公金負担の増加」など様々な反応が見受けられる。そして何より教育は開かれているべきと言う前提を改めて確認できた。今回の騒動で改めて明らかになった既存のシステムの歪みに対して、私たちは一度「大学」について向き合ってみる必要があるのではないだろうか。この連載では学生や教員、経営者や行政の立場を俯瞰し、広く日本の大学、もしくはそれ以上のことについて向き合ってみることである。
次回では慶應義塾大学の学費構造について取り扱う。
(安藤叡)



