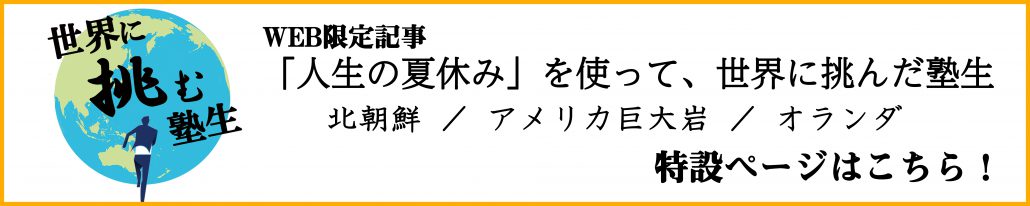「すみません、アムステルダム大学の建物ってどこにあるか分かりますか?」「大麻屋が見えるだろ? あそこだよ」
オランダのアムステルダムで留学生活を始めて1週間が経った頃、通りすがりの住民と交わした実際の会話だ。留学先のアムステルダム大学には、いわゆる「キャンパス」がない。教室が市内に点在しており、運河が複雑に入り組む迷路のような街で探し出さなければならない。
最初の講義を受けた建物は、よりにもよって「大麻屋」の目の前にあった。
「大麻屋」と訳したが、実際には「coffeeshop(コーヒーショップ)」と呼ばれている。オランダでは、店舗の立地や大麻製品の取引量など、厳格な条件を満たしたコーヒーショップのみが、大麻の売買を許可されている。

オランダ国内でも特に首都アムステルダムでは大麻の取引や使用が盛んだ。中心街を自転車で走っていると、コーヒーショップから漏れた「大麻臭」がそこかしこから漂ってくる。ある時はやたらと煙が吹き付けてくると思えば、前を走る自転車の男性が吸っていたこともあった。
現地の大学生にとっても大麻は身近な嗜好品だ。寮で同じ階に住む同級生は、初対面の筆者に「一服する?」と手巻きの大麻を勧めてきた。片手には、小さなプラスチックの袋。そこから乾燥させた大麻を取り出し、細かく刻んで器用に紙で巻いていく。袋の中に入っている乾燥大麻は3グラムにも満たないと教えてくれた。もちろん「一服」は丁重に断った。
しかし実は、オランダでは大麻を含む全ての薬物の製造、販売、所持が法律により禁じられている。
では、なぜ例の同級生は逮捕されないのか。
オランダ政府は1976年の法改正で、5グラム以下の大麻の所持を非犯罪化している。これにより、大麻の個人使用は「違法だが起訴されない」といういびつな法制度が出来上がった。
大麻の所持だけが非犯罪化されたのには、もっともな理由がある。
60年代後半から70年代にかけ、ヒッピー文化の世界的な広がりとともに、欧州では若者が薬物乱用に走るようになった。オランダで薬物の取り締まりを見直す機運が高まった頃には、すでに大麻はアルコールと同じくらい庶民に身近な消費の対象となっていた。
大麻の使用者に処罰を下す「抑圧政策」をとれば、大麻などのいわゆるソフトドラッグはハードドラッグと呼ばれるヘロインやコカインなど中毒性の高い薬物と同じ市場に流通することになる。そこで、コーヒーショップという形で正規の大麻流通ルートを確保することで、若者をハードドラッグから隔離したのだ。
先進的な薬物政策は、オランダだからこそ実現できたとも言える。16世紀、オランダ国民をカトリックに改宗させようと企んだスペインに対し、国民は独立戦争を挑んだ。独立後の長い歴史の中で、国が生き残る術として、国民は互いの異なる文化に寛容であり続けてきた。
オランダは「自由と寛容の国」であると言われる。大麻がその象徴であるとは思わないが、オランダ人の懐の深さがなければ「大麻容認社会」が成立しないことも確かだ。今日も隣室から漂う大麻の臭いに、自分ももっと寛容であるべきだろうか。
【アムステルダム=広瀬航太郎】