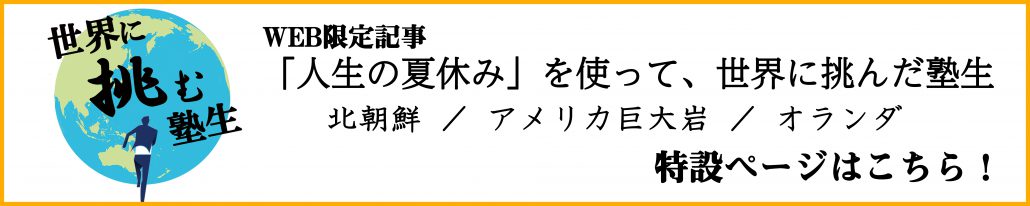思っていた以上に体は疲れていたようで、お恥ずかしながらまたも爆睡をキメてしまった。朝6時まで1度も目を覚ますことなく、岩と同化していたようだ。棚から滑り落ちないようゆっくり起き上がると、東の空には既に放射状の明るみが露になっていた。乾燥した空気と指先への負荷のせいで、指の爪が2mmほど剥がれて出血した痕がみられる。痛みで反射的に朝食の食器を放しそうになる。
果たしてこんな手で登れるのだろうかと一瞬思うが、答えは「できる」、「できない」の二択ではない。我々には上に進む以外道はない。「やる」の一択なのだ。剥がれかけたテーピングを手の甲と指に巻き直し、まだ近づいているようには見えない頂上のリップをまた目指す。
最終日の核心は、このルートを代表する超高難度のピッチ、Changing Cornerだ。出だしの数メートルはプロテクションが取れないフェイスで、あまりロープに身を預けてフォールしたくはないセクションだ。思い切りよく豪快なムーブで素早く垂壁を駆け上がると、縦に長く走るクラックが2本、目の前の凹角のコーナーに突然姿を現した。手足で登るフリークライミングとギアに立ち込むエイドクライミングを織り混ぜ、自分に可能な最高速度で核心のセクションまで前進する。Changing Cornerではその名のごとく、凹角状のコーナーから、2m右に離れたもう一つの凹角コーナークラックに水平移動する。残置されたカラビナを使い、ロープにぶら下がって肌色の花崗岩の壁に乗り込める結晶を探す。小指ほどの細さのクラックが右のクラックに見えると、手を伸ばしフィットするサイズのギアを差し込む。一発でキマるとその後もなんだか調子がいい。垂直のコーナーに身を納めながら真上に15m登りきると、いよいよ頑丈なボルトの打ってある終了点に着いた。

「登っているときに下を見てしまったら怖くないのか?」という質問を受けることがよくある。こういう場所から下を見ると、もちろん何百メートルかの空間を挟んで地面が見えるわけで、そんなものを見て何も感じない訳ではない。怖いものは怖い。ただ、登っているときは高さなど特に気にならない。シューズで乗り込む足元の形状に集中してしまうため、地面があまり視界に入らないのだ。もちろん、クライマーではない人間よりも、少しばかり高さに対して麻痺しているとは思うが。
体外から摂取していなくても、ハイになれる成分を作り出せるヒトの体は素晴らしい。今は高さも、疲労も、空腹感も感じない。こういう時はなぜだか普段よりも、自分が心と身体の底から本能的に求めるものがより明確に頭に浮かぶのである。したいこと、飲みたいもの、会いたい人、話したいことなどが、ひっきりなしに脳裏を右から左へ駆け抜けていく。まるで週末に楽しい予定を控えた金曜の夜ように、なんだか気分がいい。アドレナリン中毒の典型的な症状だ。クライマーズハイがキマってきた。
気付けば残り3ピッチ。あと100mほど登れば、「歩く」ことができる。あせる気持ちを一旦抑え、次のピッチに必要なギアしっかり確認する。俺らの生きた平成が終わっちまうんだとか、そんなどうでもいいことを口にしながら、垂直な壁に走るクラックに手足をねじ込み駆け上がる。
Changing Cornerから長らく続いていたクラックのラインが、いよいよ途絶えた。次は紆余曲折するボルトのラインをたどりながら、頂上を目指す。エイドクライミングでは、「あぶみ」と呼ばれるスリングで出来た梯子のような道具を使う。壁にささったボルトにあぶみをかけ、その輪に足を入れて踏み込み、壁から身体が剥がされないように立ち上がって次のボルトに手を伸ばす。落ちる心配はあまりないが、地味に体力が削られる。終了点が数メートル先に見えたところで、ボルトの間隔が突然広くなった。どう頑張ってもボルトに手が届きそうにはない。右に3mは離れているだろう。よく見ると、手がギリギリ届きそうなところに浅いスロットがあり、道具を使えば体を引き寄せられそうであった。が、このピッチは全てボルトラダーだと思い込んでいたため、カムなどのギアはフォローの岡田にすべて預けてしまっていた。一度岡田と同じ高さまで下降してギアを受けとることは可能だが、既に15m以上は登っていたので、時間がかかってしまう。こんなところで時間を無駄にしたくはない。
今は平成最後の大決戦。この夏は、自分にとって学生最後の夏だ。青春の最後の灯火を、これでもかと燃やし尽くすために戻って来た。止まってなんかいられない。こんな時はフリーで登ってしまえばいい。失敗したところで、横に降られながら数メートル落ちるだけだ。ディズニーシーのタワーオブテラーの方がよっぽど怖いんじゃないか。と、弱い自分を騙して戦闘体制に入る。滑り止めのチョークの粉を再度手にまぶし、つけすぎた分を息で吹き飛ばす。白く煙る視界に、次に踏む岩の形状を見いだす。これだ、と決めたポイントにクライミングシューズのつま先を押さえつけ、1センチほどの縦の溝を右手で押さえた。「ロープ出していいよ!」と、岡田に届くよう大きな声で叫ぶ。するとロープのテンションが緩み、一瞬身体がフワッと壁から離されそうになる。握り込む右手に力をいれ、体を右に傾けながら斜めの形状に乗り込む。2センチほどの溝に、ギアの代わりに指を2本差し込む。足を慎重に踏みかえ、体全体を右に移動させる。溝を左手に持ちかえ、視線は手を伸ばせば届くボルトにむけたまま、腰のラックを右手で探った。手に取ったカラビナのゲートを親指で押さえながら、頑強なボルトハンガーに目一杯手を伸ばしクリップした。
ホールバッグを引き揚げ終わり、岡田も最終ピッチのスタートに合流する頃、僕らはこの巨岩壁の一部となって東のマーセド川に影を落としていた。準備はいいかと岡田に聞くと、「Yeah Mike!」と訳のわからない返答をした。どうやら彼も相当ハイらしい。目の前には10mほど上に続くスラブ状の白い壁。そしてそのすぐ上には、淡色の絵の具が混ざったような、不思議な色の空が見えた。あそこまで登れば歩ける。クライミングシューズのレースを締めなおして、最後のフリークライミングが始まった。この高さまで全てのピッチをリードしてきた自分は、大きな自信を背後霊のように纏っていた。ギアなど使うものか。途中現れたボルトも無視して登り続ける。落ちる気がしなかった。
いよいよ傾斜が三田キャンパスの正門前の坂くらいになった。二足歩行の可能性に初めて気付いた類人猿のように、手を前にゆっくりと立ち上がった。自慢の前足はもう要らない。岩角にすれて少し重くなったロープを手で引きながら、大きな松の木の下まで歩いた。木の幹に巻き付けられるほど長いスリングを持ちあわせていなかったので、つい先程まで世話になっていた2本のあぶみを使い、カラビナでロープを固定する。「ビレイ解除!」の声は1度で岡田に届いた。引き揚げる荷物が岩角に引っ掛からないよう慎重にロープを手繰りながら、岡田の到着を待つ。こちらから岡田の姿が見えたと思いきや、写真を撮れ、と彼は両手を挙げて動かない。彼は最後までミーハーを貫いた。
時刻は18時少し前。約75時間をかけ、エル・キャピタンの頂に立つことが出来た。長いチャプターが終わった。頂上からの景色は言葉にならないほど美しく、この時自分は地球上の誰よりも幸せで満たされている自信があった。この美しい星に生まれ、こうして大自然を最大限味わいながら、今も生きていることの喜びを噛み締めた。

この岩を登りきって、誰かに何かを貰えるわけでもないのだろう。ただ、これを成し遂げることが、この先の人生において大きな意味を成すことを、2人ともなんとなく分かっていた。だから40ミリの雨予報でも山梨の岩場に突っ込んだりしたし、重りを持って長野で夜通しの岩登りもした。それらのトレーニングの日々が、今もう既に「良き想い出たち」に変わっていっている、そんな気がした。
そうこうしているうちに西の果てに陽が沈む。太陽だって忙しい。日本でも皆が同じ恒星の明るさを見ていると思うと、なんだか地球が小さく思えた。時間は僕らを待ってはくれなかった。暗がりの中でお湯を沸かしながら、翌朝下山を始めるまで滞在するキャンプサイトを整える。丁度いいサイズの岩の枕がある。平らで広い、最高の寝床だ。今日の晩飯はビーフシチューとわかめご飯。程よい疲労感とこの上ない満足感に包まれ、満天の星空の下で口にするその和洋折衷は、「美味しい」、「旨い」などという簡単な言葉で片付けられなかった。きっとこの味を、一生涯忘れることはないだろう。やはり、山で食べる温かい晩飯より美味いものはこの惑星に存在しないのだ。
◆
翌朝、エル・キャピタンの裏からハイクダウンしてキャンプ場に戻ると、見慣れた姿の日本人2人が、トイレ近くの大岩を触って遊んでいた。山岳部の奴等を見ると、なんだか急に安心した。ヨセミテに入る前に、ホールサイズのチョコケーキと大好きなモンスターエナジーを買っておいてくれたらしい。そのままかぶりついたそのケーキは、涙が出るほど美味かった。
3日後には、彼らともう1つの大きなピーク、ハーフドームの北西壁を登ることになっていた。さすがにレストが必要だったので、明日、明後日はレンタカーを独り占めして1人出掛けることに。ヨセミテでガイドをする仲間の1人を尋ね、メアリグレイスらと再会し起こったエピックについては、またいつか機会があればお話しさせていただくことにしよう。
◆
9月の自分の卒業式のことなんてすっかり忘れていて、あとから聞いた話では名前が呼ばれていたとのこと。帰国したら学位記を三田に受け取りに行かなければならない。だが、そんなことはどうでも良かった。僕らはやってやったのだ。最高にアツい夏を乗り越えたのだ。El Cap Meadowで撮ったクライミングチーム最後の集合写真は、一生の宝物となった。

(寄稿:駒井祐介)
【2年前の冒険はこちら!】