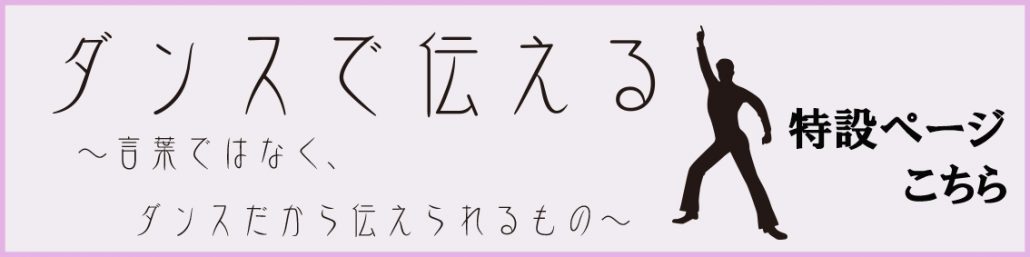リオパラリンピックの閉会式で、ソロを務めた日本人ダンサー、大前光市さん。片足が義足という、「かかしのダンサー」として活躍している。ハンディキャップを抱えながらもダンスを続ける彼は、何を伝えようとしているのだろうか。
大前さんは高校時代から本格的にダンスを始め、大学でバレエを専攻した。そして、バレエ団の選考を受けようとした矢先、交通事故に遭う。彼は左膝下の切断を余儀なくされ、掴みかけた夢はこぼれ落ちた。
はじめはどうにかして普通のダンサーに戻ろうと葛藤していた。しかし「だんだんと普通の人みたいに踊れるようになってきたね」という褒め言葉をかけられた時、目指すダンスに違和感を覚えた。これまでのように踊ることが正解なのか。
考えが変わったきっかけは、義足なしのダンスを仲間が認めてくれた瞬間だった。短い脚のままでも、ありのままの自分のダンスを見せることで、次第に観客からも良かったと評価されるようになった。彼は自分のダンスを信じられるようになり、堂々と踊れるようになった。「ほかの人とは違うやり方で同じ立ち位置に立てば良い」。自分らしさを大切にする大前さんのスタイルが確立した。
大前さんは自身のパフォーマンスを通じて、「マイノリティ、普段あまり見られていない人のかっこよさがもっと評価されるようになってほしい。それが普通になってほしい」と話す。
ダンスは言葉を必要としない原始的なコミュニケーションだ。国境を越えて理解され、世界中で踊られている。それに加えて、誰もが自分らしい形で気軽に自分を表現することができる。「言葉を使わないことで、私たちはもののありのままの姿を見ることができ、より生々しさを感じるのではないか」と大前さんは指摘する。ダンスの持つ原始的で身体的なエネルギーが人の心を動かす。さらに感情という心的なものが加わり、共鳴することでダンスは人々に共感されるという。
ハンディキャップはある意味マイナスだと受け取られるが、かえって印象に残りやすいパフォーマンスができるのではないか、と大前さんは話す。「特殊だからこそ魅せ方を工夫すれば『一点物の美術品』になることができる。この良さを一般的に広めていきたい」。その人だけが持つかっこよさを引き出すのに成功すれば、コンプレックスを打ち破り、自信に変えることができる。より「自分らしいダンス」を目指し、大前さんはダンスに向き合い続ける。
(大津こころ)