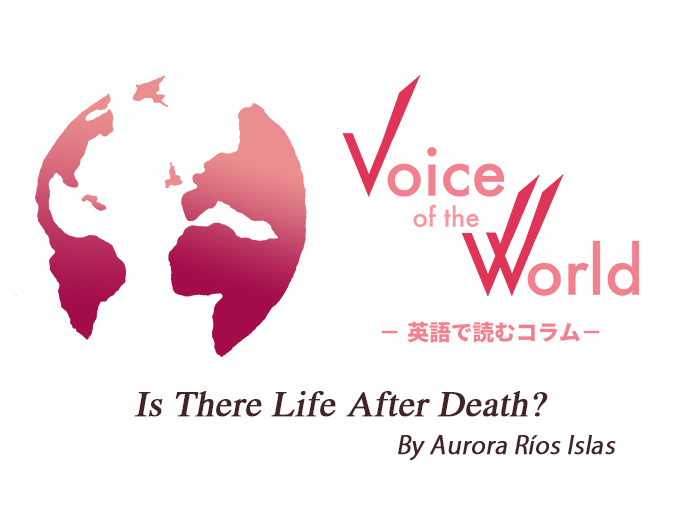
友人とのパジャマ・パーティーとピクニックは、欧米では一般的なレクリエーションだ。しかし、11月の夜に、洗剤を入れたバスケットを片手に墓地で開催するピクニックとなると、話が違う。死とは普遍的な概念だが、その捉え方は世界各国で異なる。日本人が盆を、ポーランド人がサドゥスキーを、そしてメキシコ人がディア・デ・ムエルトス、「死者の日」を過ごすように。
スペイン語の名詞には性があり、「死」という言葉は女性名詞である。なるほど、Catrinasと呼ばれる骸骨が、美しいドレスと花とで優雅に着飾られることにも説明がつく。加えて、アステカ人*にとっての「死神」は、Mictecacihuatlという女神だった。Catrinasは、11月1日と2日に、メキシコとその他の至る場所で姿を現す(007シリーズ最新作『スペクター』を参照)。
死は、誰にとっても決して耳に心地良い話題ではないが(メキシコ人の大多数にとってはタブーである)、この2日間ばかりは、死から目を逸らすことなく、故人に敬意を表する。各家庭、役所、道端など至る所に祭壇が置かれ、ろうそく、花、果物、ナッツ、そして死者の大好物・テキーラのボトル(何か問題でも?)で彩られる。
ここで、メキシコ人の精神が、先住民とスペイン人間での無意識で暴力的、かつ予期せぬイデオロギーの衝突によって生まれたということを思い出したい。精神的に不安定なメキシコ人の先祖たちが、骸骨の形をしたチョコレートが友人に最も好まれるプレゼントだと思い当たったとしてもおかしくはない。もしくは、死が人々を来世へと「連れ去っていく」様子を面白おかしく風刺した詞・calaveritasも、その産物だろうか。メキシコでは、むやみにジャーナリズムを行使することは危険と考えられているため、calaveritasこそが政治家や政治制度を批判する者にとっての安全地帯なのだ。
死者の日は、もはや宗教的慣習としての意味は薄れ、単純に伝統として受け継がれている。では、死の後には何が待ち受けているのだろうか。死は普遍的であり、逃れられない。この認識は変わらない。大切なのは、残された者が、死の後にも生はあると思い続けることだ。人は、死んで弔われるのではなく、生きることで愛されるのだから。
(文:アウロラ・リオス、訳:広瀬航太郎)
*1519年、スペインに侵略される前の首都・テノチティトラン(今日のメキシコシティー)の住民



