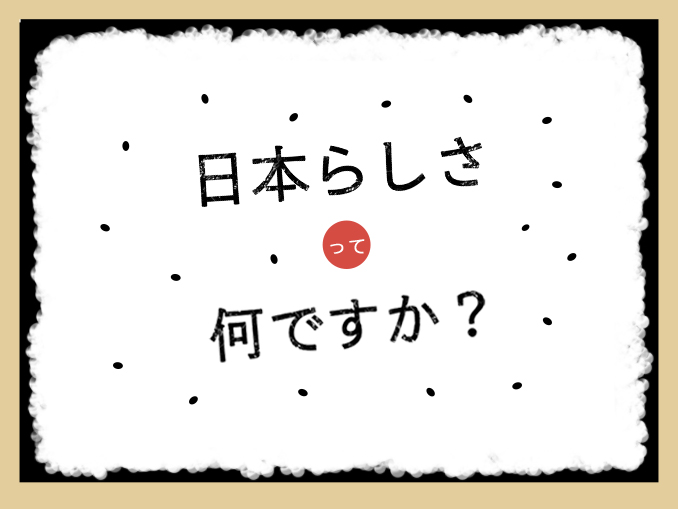
ドイツ人の友人と一緒に、巻き寿司作りをしたことがある。その際、一番驚かれたのは、味でもなく、巻き簾で巻く工程でもなく、「卵焼きを菜箸だけを使って巻いた」ことだった。
フォークやナイフのように金物で「突き刺す」のではなく、木で「挟む」箸文化を育んだところが日本らしい。箸とは、一面では主目的が曖昧であり、言い換えれば機能性に富んだ道具である。つまむことも、刺すことも、溶くこともできる。まさに、「和」はどこでもいい顔をするものだ。
箸に使われる木には、人々の手に馴染む丸みがあり、どんな使い方も受容するおおらかさがある。和食以外の料理を食する場合にも適しており、カトラリーのように持ち換える必要がない。箸を使うことで、日本人は異国の食文化を受け入れてきたのではないだろうか。
「日本人は固有の文化を継承していく姿勢が弱く、変化を受け入れるがゆえに無国籍になっている」という批判もあるだろう。だが、長年国内外で多数の建築を手がけてきた隈さんはこう話す。
「日本はこう、世界はこうと考えない方がいい」
例えば、今や和食の代表格と考えられている天ぷらは、元々は西洋から伝来した食べ物で、「テンペイロ」と呼ばれていた。このように、外来の異質なものをカタカナで表すことで上手く受け入れるところが日本人らしいと小山さんは語る。カタカナだったものが日本に定着した時、人はそれを漢字で表記したくなるのだという。
カタカナから漢字への変化と同様に、日本の文化もまた、漢字からローマ字へと姿を変え、世界に受け入れられてきた。今日、海外に住む外国人でも箸を使いこなせる人口は増えつつある。箸からHashiへ、異質性を受け入れる日本らしい柔らかさと温かみが世界に伝わっていくことを、切に願う。
(広瀬航太郎)



