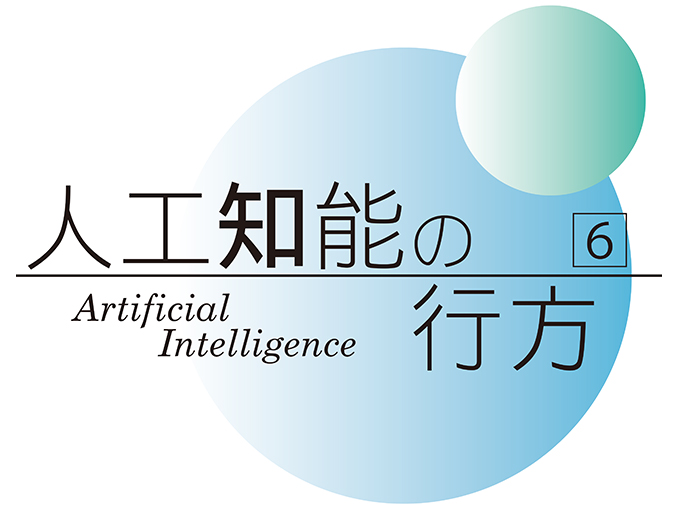
「その日は、雲が低く垂れ込めた、どんよりとした日だった」――昨年、小説『コンピュータが小説を書く日』が第3回星新一賞の1次審査を通過した。まさにこの題名が、ここで何が起こったかを示している。この作品は、人工知能研究を行う公立はこだて未来大学の松原仁教授を中心としたプロジェクトの、いわば「研究成果」だ。
「きまぐれ人工知能プロジェクト 作家ですのよ」。このプロジェクト名に星新一の作品、『気まぐれロボット』と『殺し屋ですのよ』が見え隠れするように、研究は、星新一のような面白い小説を人工知能によってつくることを目標に始まった。
Microsoft社の「りんな」のように、人工知能は短い言葉を生成できるようになった。しかし、その文を連ねていくと一文ずつ別人が書いたような文章になってしまう。意味の通る長い言葉をつくるのはまだ難しい。
星新一は、短編小説より短いショートショートとよばれる作品を1,000も残している作家である。その特徴は、話のオチがはっきりしていること、時代背景がほとんど設定されず話が複雑でないことだ。これは人工知能で扱う話には最適であった。
そもそも作家はどのように小説を書いているのか。とはいえ作家自体がごく少数であり、この答えは作家本人でさえも分からないかもしれない。松原教授らは作家のインタビューやエッセー、講演会の言葉からアイデアの出し方などを探った。
次に、計量書誌学の観点から星新一の作品を分析し、一文の字数、使用する単語、一つの段落の文章量などの傾向をつかんだ。また、ショートショート全作品についてネタの種類、オチの手法といった観点からパターン分類を行った。これらのアプローチによって情報を集めていったのだ。
星新一を「超える」作品を目指す。分析して得た話のパターンを今までになかった形で組み合わせ、それを実際の小説の言葉にしていった。
『コンピュータが小説を書く日』の制作では、アイデアを小説の文章にする部分を人工知能が行った。作品の展開パターンがあれば、そこから数十万の作品を生み出すことも難しくはない。
しかしながら、話を構成する上でのパターンの組み合わせや、数十の作品から応募作品を選考したのは人間だ。また、作品中に言葉の使い方で正しくない点もみられ、文章自体の精度はまだ最高水準とはいえない。
人工知能だけで一つの質の高い小説を書くことはできるのだろうか。小説は勝ち負けのあるチェスや将棋とは異なり成果の到達度が明瞭でない。文学賞においても評価には主観が入り込む。
「作家ですのよ」で研究中のプログラムでは、人工知能を用いてそこに点数による評価を与えることを目指している。収集したデータをもとに、星新一らしさ、小説の良し悪しなどを点数化するのだ。これが可能になれば、制作した膨大な数の作品を自ら評価し、点数の高い賞に応募できる優れた作品を選び出せる。
松原教授が思い描く、人工知能が小説を書く未来はどんなものか。スマートフォンで自分の好きな小説を入力すると、人工知能がつくったその人好みの特徴を持つ小説が毎日手元に届けられる。未完の作品が完結する時が訪れるかもしれない。人工知能の強みを上手く引き出してできる、人と小説の新たな形だ。
『コンピュータが小説を書く日』の先には、「ある作家による優れた小説」ではない「誰かがつくったその人好みの小説」が生まれる未来が待っている。小説の向かう新たな道が切り開かれつつある。
(青木理佳)



