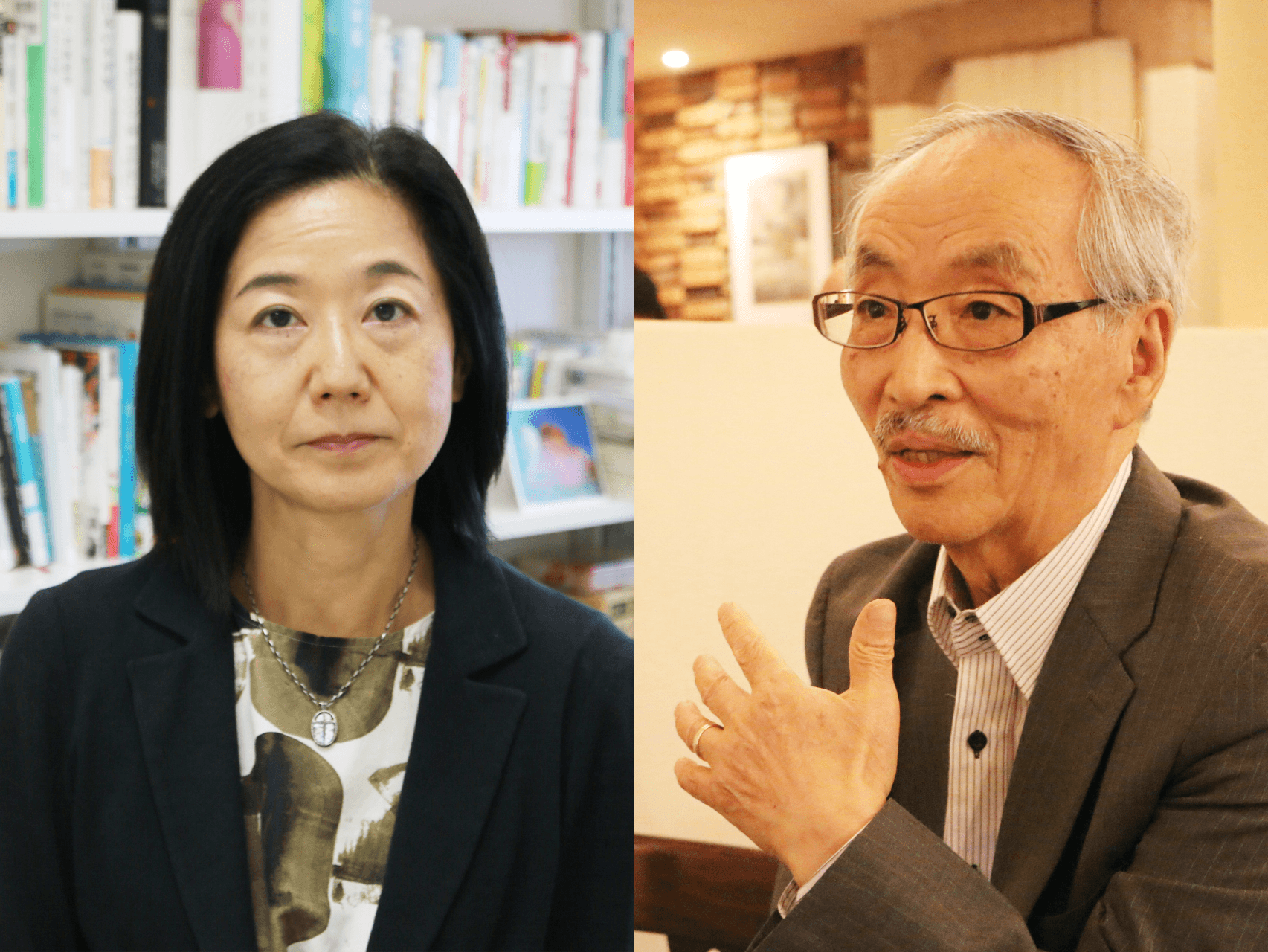
(左から)野村浩子さん、金子雅臣さん

女性が職場のセクハラを告発する世界的な動きが、日本にも広がっている。きっかけは、財務省の福田淳一前事務次官がテレビ朝日の女性記者にセクハラ発言を繰り返していた問題が明らかになったことだ。女性記者は、当該発言を録音した音声データを『週刊新潮』に提供していた。
元日本経済新聞編集委員で女性の労働問題に詳しい淑徳大学の野村浩子教授は、「多少過激な方法でなければ明らかにすることはできなかった」と記者の行動に理解を示す。
労働政策研究・研修機構が2015年に行った調査によると、回答企業1711社のうちセクハラ対策に「取り組んでいる」と答えたのは59%にとどまった。男女雇用機会均等法は事業主に対しセクハラ防止措置義務を定めるが、実質40%近い企業が違法状態を放置していることになる。多くの場合、被害者側が泣き寝入りせざるを得ないのが現状だ。
「セクハラに対して罰則付き禁止規定を設けていない先進国は珍しい」と野村教授は指摘する。日本政府は国連の女性差別撤廃委員会から「セクハラに関する禁止・制裁措置」を法令化するよう再三の勧告を受けてきたにもかかわらず、応じなかった。
政府がようやく重い腰を上げたのは、福田前事務次官の問題発覚後だった。各省庁の幹部にセクハラ防止研修を義務付ける「緊急対策」を決定したが、「噴飯もの。セクハラをしっかりと定義づけ、禁止事項を設けなければ何ら実効性は期待できない」(野村教授)。
ただし、禁止規定の検討には課題もある。職場のハラスメント研究所代表の金子雅臣さんは、「ハラスメントは『べからず集』を作れば対応できるというものではない」と警鐘を鳴らす。「セクハラに線引きを求めると、『胸ではなく髪ならセーフなのか』とボーダーラインの議論になる」
セクハラを人権問題として捉えられない意識の低さは、閣僚の「セクハラ罪という罪はない」との発言にも表れている。金子さんは長年、東京都職員として窓口でセクハラ相談を受けてきたが、大半のケースで加害者に自覚はなかった。「日本人は特に人権意識が遅れている。結局は法律を先に作り、意識を改善していくしかない」
現行法でセクハラを提起しているものは均等法のみだ。しかし、そもそも均等法は事業主を指導するための法律であり、当事者間の問題であるセクハラの規定は馴染まない。罰則規定を検討するのであれば、現行法の改正ではなく「性差別禁止法」の創設について議論を進める必要がある。
国際労働機関(ILO)は、来年にも職場でのセクハラをなくすための国際条約を制定する方針を固めた。条例が批准されれば拘束力が生じる。勧告から逃れ続けてきた政府が法整備へ動き出すのか、次の一手が注目される。
(広瀬航太郎)




